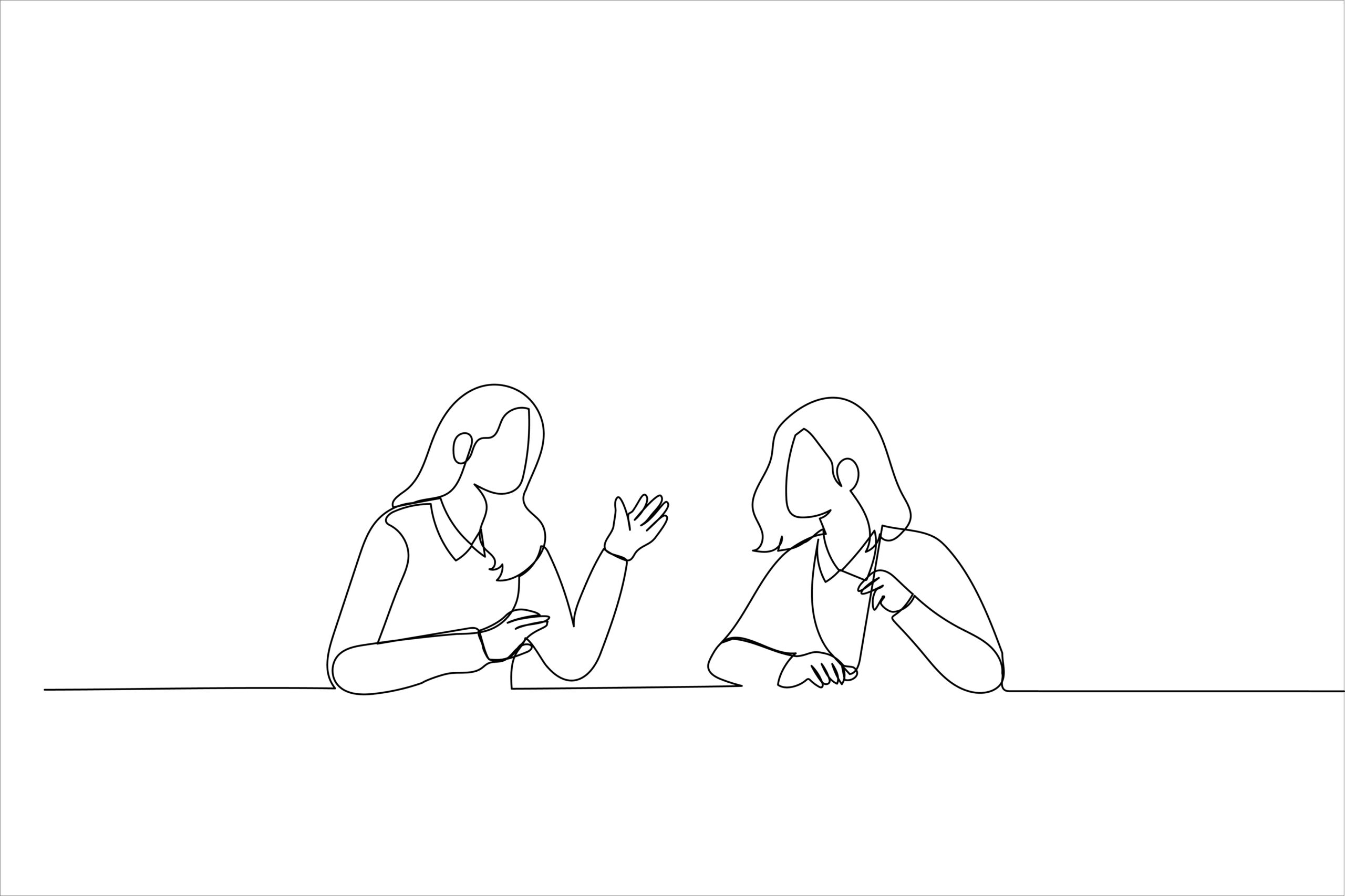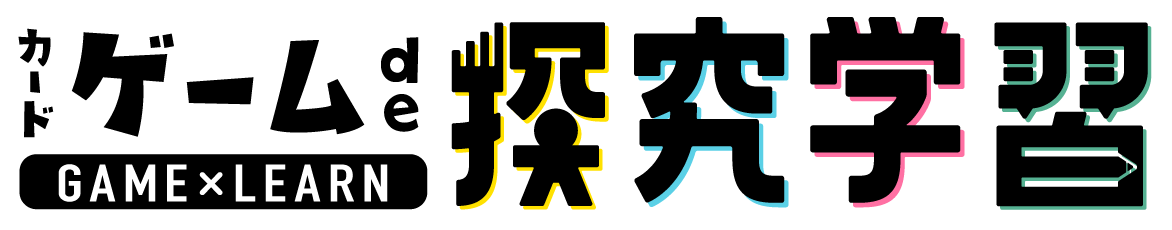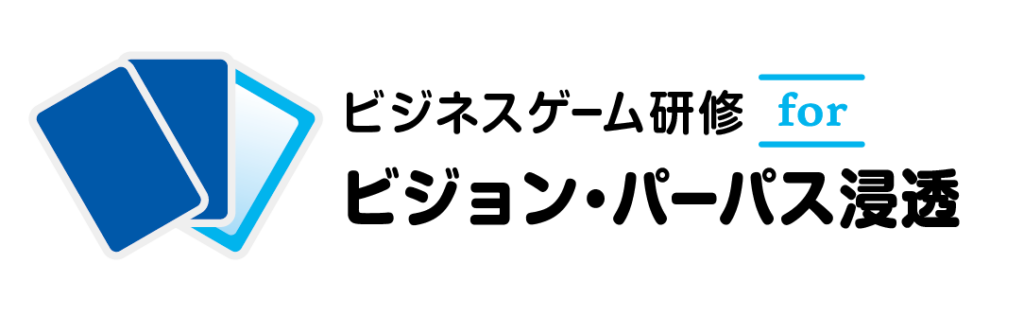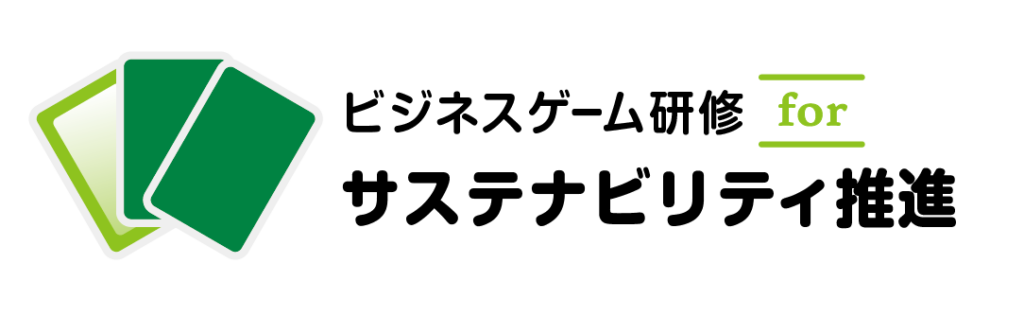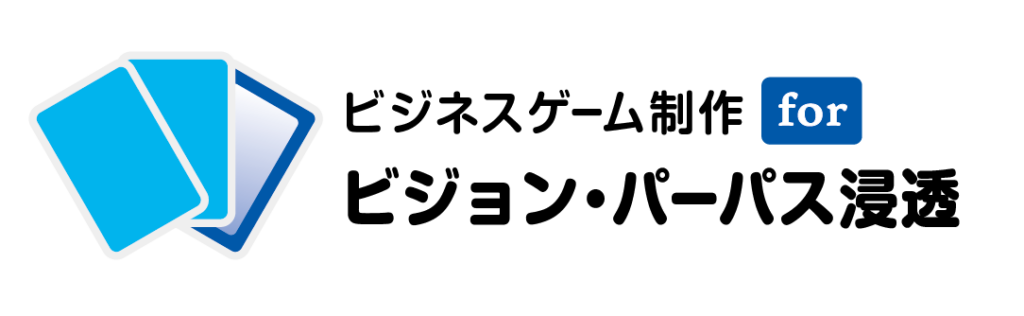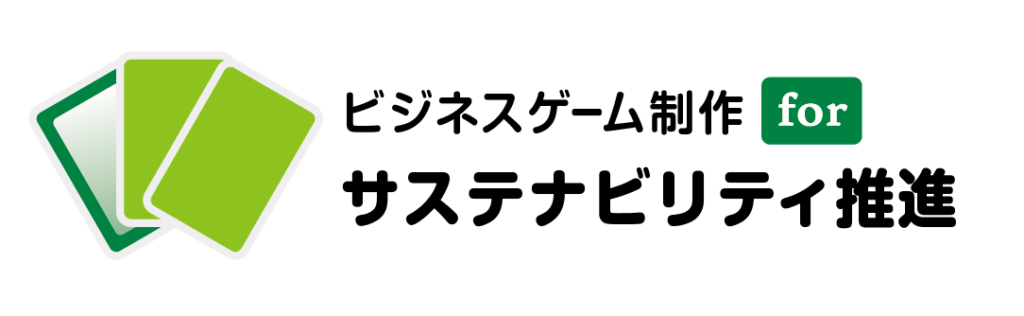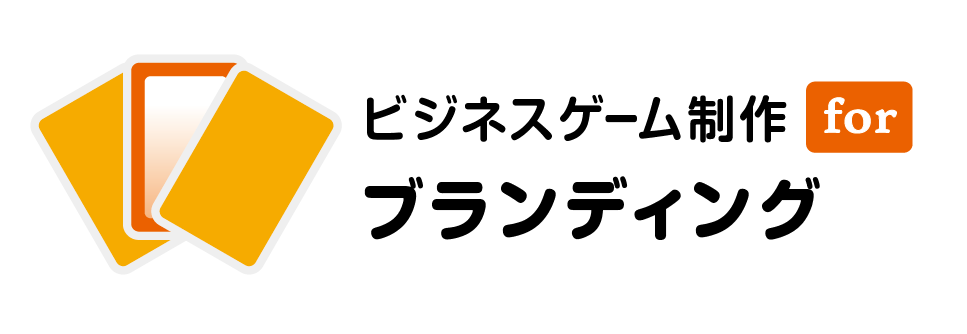OJTとは?OJTを成功させるためのポイントを簡単解説!
- 最終更新日:2025-11-04
OJTとは何か? そして、OJTを成功させる(機能させる)ためにはどのようなポイントを押さえておく必要があるのかについて、簡単に解説します。
OJTとは
OJT(On-the-Job Training)とは、実務(日常的な業務)を通して仕事のやり方を指導する教育手法です。企業の人材育成においては、主に、新入社員や若手社員などの業務に習熟していない方々がOJTの育成対象となります。
OJT と Off-JT
Off-JTとはOJT以外の場(職場の外)における教育手法を意味するものであり、具体的には研修やワークショップ・セミナーなどが挙げられます。
OJTは実務の習熟度を高めることが目的であるのに対して、Off-JTでは基礎的なビジネスの知識・スキル・マインドの習得が目的になります。
まずはOff-JTの場で基礎を学び、その後に配属先でOJTを行うパターンが一般的です。
| OJT | Off-JT | |
| 目的 | 実務の習熟度の向上 | 基礎的なビジネスの知識・スキル・マインドの習得 |
| 手法 | 実務経験 | 研修やワークショップ、セミナーやeラーニングなど |
| 実施時期 | 本配属後 | 入社直後 |
| 実施場所 | 職場内 | 職場外 (研修施設) |
表. OJTとOff-JTの違い
OJT制度とメンター制度
OJT制度の類語に、メンター制度があります。
育成対象者の実務スキルの習得を目指すOJT制度に対して、育成対象者のメンタルケアやキャリア支援を行うものがメンター制度になります。メンター制度では、直属の上司とは別の人材(先輩社員)がメンターを担うケースが一般的です。業務上の関りが無い間柄だからこそ、悩みの相談がしやすくなります。
| OJT制度 | メンター制度 | |
| 目的 | 実務スキルの習得 | メンタルケアやキャリア支援(悩みの相談) |
| 指導者 | 上司や部署の先輩社員 | 先輩社員 |
表. OJT制度とメンター制度の違い
OJT とオンボーディング
オンボーディングとは、組織の新メンバーをサポートする取り組みを意味します。
オンボーディングの由来は「on-board(乗り物に乗る)」という言葉にあるように、新メンバーに組織という乗り物を乗りこなしてもらう(組織に馴染んでもらう)ことが、オンボーディングの目指す姿です。
この意味において、オンボーディングとはOJTを含めた包括的な人材育成パッケージであると捉えられます。
ご案内
OJTを成功させるためのポイント(OJT指導者の心得)
コミュニケーションを使い分ける
OJTにおいては、ティーチングを基本としたコミュニケーションが主体になりますが、それ一辺倒になるのは好ましくありません。育成対象者の状況(仕事の習熟度やメンタルの状態)を加味しながら、コーチングやカウンセリングなどの適切なコミュニケーションを取り入れることが推奨されます。
ティーチング(Teaching)
ティーチングは、教育や研修の中で使われることの多い手法です。
ティーチャー(指導者)がクライアント(育成対象者)に対して教える、指示型のコミュニケーションです。ティーチングは「育成対象者が知らないことを教える場面」で効果を発揮します。育成対象者が初めて行う作業や不慣れな作業に取り組む際に有効な手法です。
<注意点>
ティーチングでは、育成対象者が教えられた以上のことをできない(やってはならない)と思う、受け身・指示待ちになることが懸念されます。ティーチングで一方的に伝えるばかりでなく、時にはコーチングを取り入れるなど、双方向のコミュニケーションを心がけましょう。
コーチング(Coaching)
コーチングは、ビジネスやプロスポーツにおける個別指導に使われることの多い手法です。
コーチ(指導者)がクライアント(育成対象者)の中にある答えを導き出すために、承認・傾聴・質問・提案などのスキルを用いて行う、目標指向型のコミュニケーションです。コーチングは「育成対象者が自分で考える必要がある場面」で効果を発揮します。育成対象者に自発的な気付き・発見を促したい時に有効な手法です。
<注意点>
コーチングは育成対象者の知識・スキルが足りない場合においては、その効果を発揮しにくい特徴があります。経験の少ない新入社員に対するOJTでは使いづらい手法ですが、中途入社社員に対するOJTには取り入れる余地があります。
ご案内
カウンセリング(counseling)
カウンセリングは、キャリア相談やメンタルケアの場面で使われることの多い手法です。
カウンセラー(指導者)がクライアント(育成対象者)の心や体の不調・悩みに向き合い、傾聴・援助・助言・指導などを使い分ける、受容型のコミュニケーションです。カウンセリングは「マイナスの状態をゼロ(フラットな状態)にする場面」で効果を発揮します。育成対象者のパフォーマンスが落ちている際のコミュニケーションに有効な手法です。
やってみせる・言って聞かせる・させてみる・褒める
「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば、人は動かじ」。
この山本五十六の格言にOJTを成功させるためのポイントが詰まっています(この観点において、OJT指導者と育成対象者の両者が留意すべきポイントをご紹介します)。
① やってみせる
見たこともやったこともない仕事を最初から上手くできる人はいません。OJT指導者が育成対象者の前で「やってみせる」必要があります。
- OJT指導者が留意すべきポイント
仕事はいつもの自分のペースで行うのではなく育成対象者が見て分かるようなスピードでやってみせます。可能であれば1つ1つの作業を解説しながら進めると良いでしょう。
- 育成対象者が留意すべきポイント
指導者がやっていることをよく観察しながら、自分がその仕事を再現できるように整理する目的でメモを取りましょう。作業手順を確認したり、分からないことは質問する姿勢も大切です。
② 言って聞かせる
言われた仕事をこなすのではなく、自ら主体的に仕事に取り組んでいく。そんな人材を育成するには「仕事に誇りとやりがいを持てるように導く」必要があります。
- OJT指導者が留意すべきポイント
仕事の意義(誰の何の役に立つのか)や仕事の進め方(1つ1つの作業の必要性や合理性)をきちんと説明しましょう。育成対象者の主体性を育む観点では、一から十まで説明するのではなく「問いを投げかけながら相手に考えを促すこと」も大切です(育成対象者としても、自分自身で答えに到達する方が、納得感・やる気が高まります)。また、この問いを通じたコミュニケ―ションは、指導者と育成対象者の絆を深める良い機会にもなり得ます。
- 育成対象者が留意すべきポイント
先入観を持たずに教わったことを素直に捉えましょう(特に、中途入社者は過去の経験や前職での常識に囚われる傾向があるので、アンラーニングする意識をしっかりと持つことが重要です)。また、「ただ説明を聞くだけ」の受け身な姿勢は好ましくありません。自身が教わる立場であることを十分に自覚して、積極的に質問や確認をすることを意識しましょう。
③ させてみる
これまでに指導者として「①やって見せ」「②言って聞かせた」ことが、育成対象者にどれだけ伝わっていたかを確認するために、実際の仕事をさせてみましょう。
- OJT指導者が留意すべきポイント
慣れた人がやればすぐに終わること・簡単なことでも、不慣れな人が行う場合は思った以上に時間がかかるものです。「作業ペースが遅い」と感じても、イライラしたり、急かしたり、途中で作業を奪ったりせずに静かに見守りましょう。また、育成対象者の仕事の習熟度に応じて仕事の範囲や難易度を調整する工夫も必要です。なお、優しい指導者の中には、仕事に不慣れな育成対象者に対して手取り足取り教えるような関わり方をされるケースを見受けます。それは一概に悪いことではありませんが、育成対象者の主体性や自走力を育む観点では、一歩引いて見守ることも大切です。
- 育成対象者が留意すべきポイント
上手くできなくてもいいので、まずは仕事を覚えるつもりで取り組むこと、一生懸命やってみることが大切です。その上で、分からないことを自分一人で抱え込まずに素直に質問することを意識しましょう。「分からないこと」は悪いことではなく、むしろ、良いことです(なぜなら、分からないことは改善点であり、より良い仕事をできるようになるためのシグナルになります)。
④ 褒める(評価・追加指導)
何事もやりっぱなしはよくありません。「③させてみた」ことに対してフィードバックをすることが重要です。OJTの観点では、育成対象者の意欲(モチベーション)を高める目的で「褒めること」に重点をおくことを推奨します。
- OJT指導者が留意すべきポイント
フィードバックをする上では、育成対象者が「どのような考えのもとに、どういう風に仕事を進めたのか?」というプロセスに焦点を当てましょう。そうすることで、「よく頑張りましたね」といった大雑把な褒め方ではなく、「その考え方は素晴らしいですね」「仕事の結果はまだまだですが、仕事の取り組み方は正しいですよ」という具合に、実のある褒め方をしやすくなります。その上で「次はもっとこうすると良いですね」という指導を展開しましょう。できなかった点を詰めるような減点的な指導ではなく、加点的な指導(できている点を認めて、さらに前進するための指導)を推奨します。
- 育成対象者が留意すべきポイント
自分の何が褒められているのか良く分からない場合は、自分から「具体的に私のどういった点が良かったのでしょうか?」と質問するようにしましょう。また、褒められたことに満足するのではなく、自分ができていない点=改善点に向き合う謙虚さを見失わないことを意識しましょう。
OJTを成功させるためのポイント(組織としてすべきこと)
OJT指導者や育成対象者が頑張ることはOJTを成功させる上での必要条件であって、それだけでは十分ではありません。組織としてすべきことをきちんと行うことが肝要です。
人材育成計画の立案
新入社員や若手社員などの育成対象者が成長を遂げ、リーダーとして会社の次代を担うまでに至る道のりを考えると、OJT単体よりも、より大きな視点で人材育成を考える必要があります。
人材育成の目標を定め、1on1ミーティングやメンター制度、オンボーディングやOff-JTなどの、さまざまな人材育成の手法や制度を検討し、自社に最適な人材育成の計画を立案することが強く推奨されます。
この全体的な人材育成計画の中でOJTが担う役割が明確に定義されることで、無理のないOJTを運用しやすくなります。
ちなみに、人材育成計画が無い場合でも、現場のOJT指導者の努力によってOJTが機能するケースはあります。ですが、そのやり方は持続的なものではありません(長期的視点においては属人的運用は破綻の道を進みます)。
OJT指導者の育成
業務に精通している人材であれば、誰でもOJT指導者になれるわけではありません。
コーチングのスキルやハラスメント防止のためのノウハウ、DE&Iの知識など、OJT指導者のスタートラインに立つ上で学ぶべきことはたくさんあります。もちろん、その手前の話として、指導者としての適性というものもあります。
OJT指導者としての要件を丁寧に言語化し、また、OJT指導者候補がきちんとOJTを行えるようになるための組織的な支援が求められます。
OJTに関する企業の取り組み事例
東京ガス
“わたしたちの育成の基本は「人は仕事を通じて成長する」ということです。また、わたしたちは、個人の能力は、会社から与えられる研修制度によって開花するのではなく、あくまでも本人の自発的な成長意欲が原動力になると考えています。そのため、育成ではまずOJTを基本として、それを補完するためのツールとしてOFF-JTを用います。そこに本人による自己啓発を加えて、三位一体による、より理想的な能力開発を目指しています”
大和ハウス工業
“「OJTエルダー(OJTは、On the job trainingの略)」に任命された社員が、新入社員の状況を充分に把握しながら、部門内外の先輩社員と連携を取り、自らが中心となって「職場での指導・育成」を推進する制度です。本制度により、新入社員の実務だけではなく、人間力の成長も支援します”
LINEヤフー
“新卒社員と若手先輩社員で開催するランチ会の飲食費用について、費用補助を行う施策です。OJT担当社員が、実業務を進める上での知識やスキルの習得・仕事の進捗確認などのサポートを行うのに対し、若手先輩社員は新卒新入メンバーが気軽に相談できる他組織の「お兄さん」「お姉さん」のような存在です。新卒研修やOJT期間中にはできない、新しい社内の人間関係づくりのきっかけとして活用されています”
GCストーリー
“新卒3年目までOJT担当がつき、ポータブルスキルマップをもとに月1回以上の頻度で1on1を実施しています。仕事に対するフィードバックの機会をこまめに設けることで、成長を最大化します。適切なストレッチゾーンに身を置き、自分の頭で考えながらスキルを伸ばしていきます”
参考:成長支援 – GCストーリー株式会社 採用サイト
この記事の著者について
執筆者プロフィール
池田 信人
自動車メーカーの社内SE、人材紹介会社の法人営業、新卒採用支援会社の事業企画・メディア運営(マーケティング)を経て、2019年に独立。人と組織のマッチングの可能性を追求する、就活・転職メディア「ニャンキャリア」を運営。プロジェクトデザインではマーケティング部のマネージャーを務める。無類の猫好き。しかし猫アレルギー。
Contact Us
ご相談・お問い合わせ
相談内容の例
- 実施する際のおおまかな費用感や必要な環境を確認したい
- 数あるビジネスゲームの中から、自社に合うビジネスゲームが何かを知りたい
- 自社の課題に対して、ビジネスゲームでどんなことができるのか、事例を聞きたい
- ビジネスゲーム制作について興味があるので、少し詳しい話を聞きたい
営業時間:9時~18時(平日)
サービスラインナップ
ビジネスゲーム
サイトマップ
Copyright © 2016 Project Design Inc. All Rights Reserved.