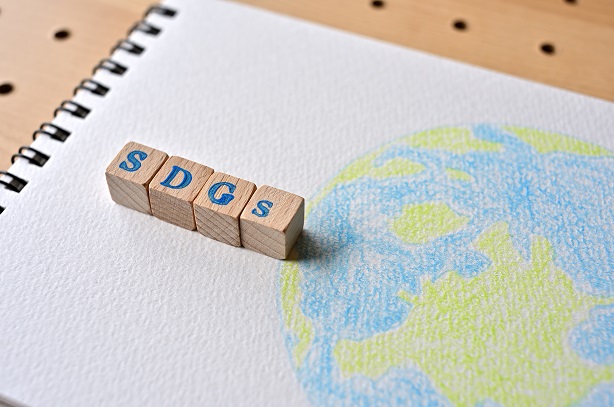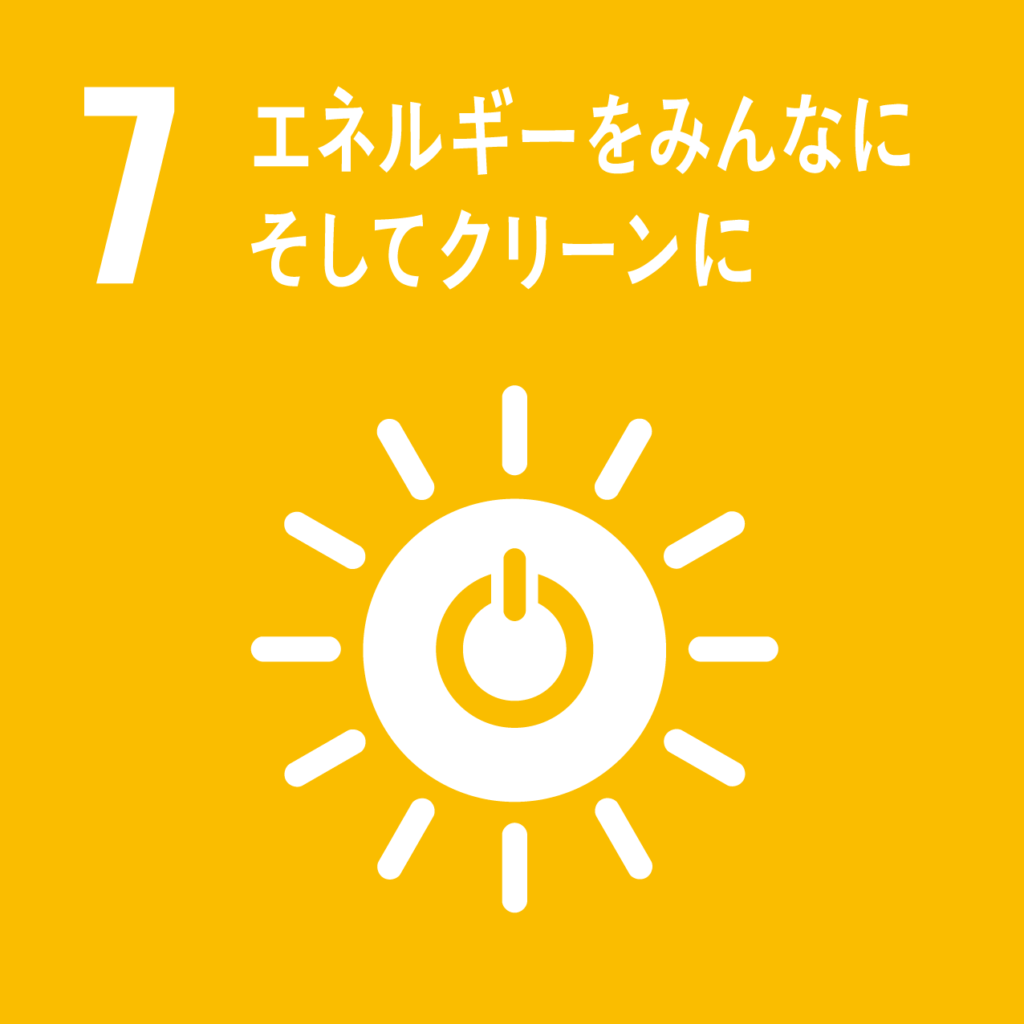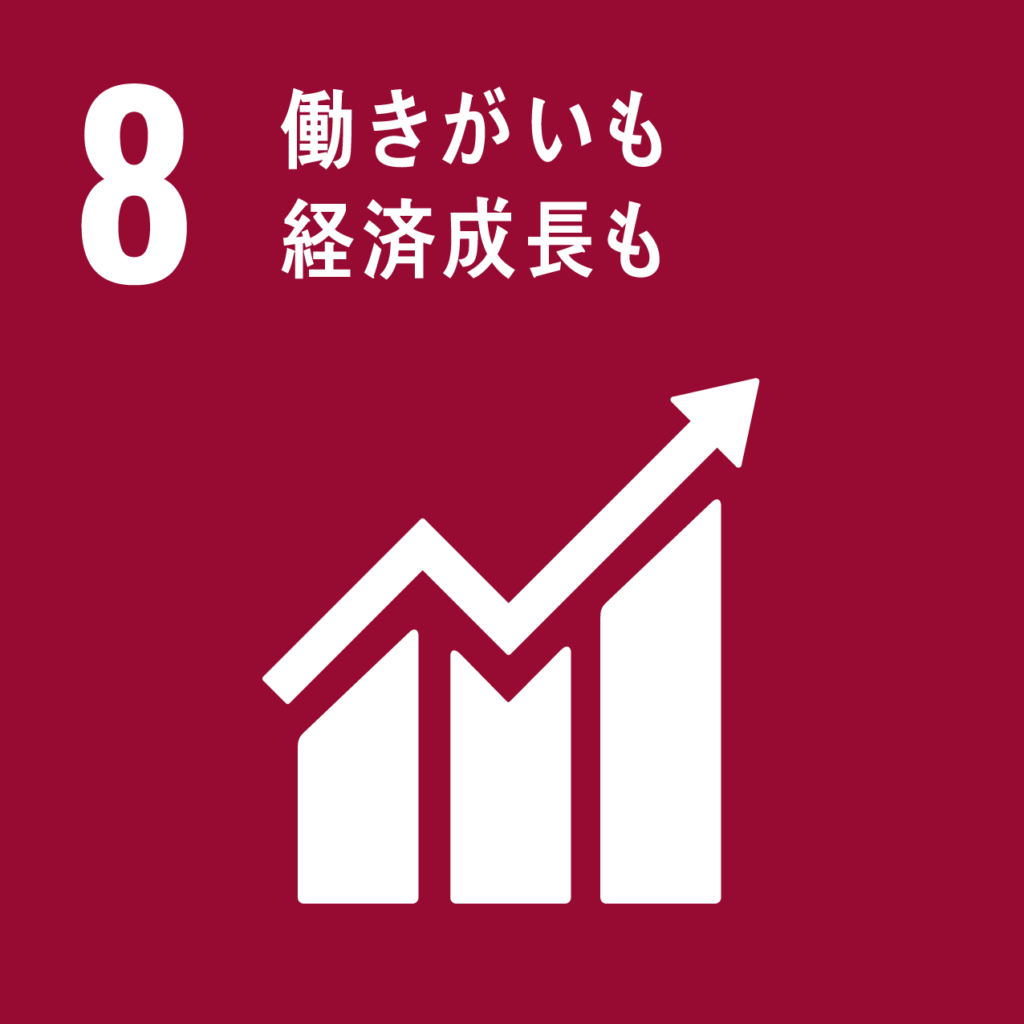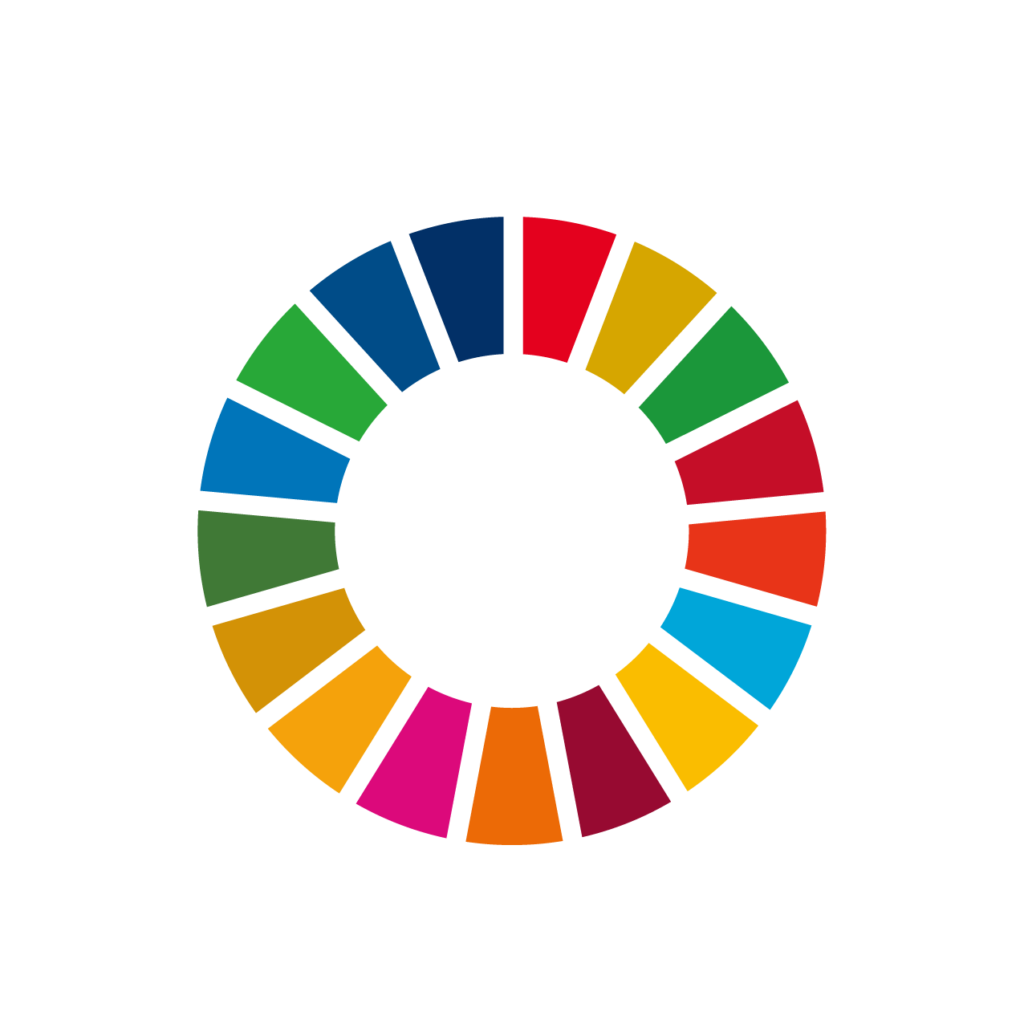SDGs2「飢餓をゼロに」の企業の取り組み事例・私たちにできること
- 最終更新日:2024-12-26
- SDGs2「飢餓をゼロに」
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する(End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture)
本稿では、このSDGs2の理解を深め、実際に企業が取り組みを進めている事例を知り、私たちにできることを考えていきます。


SDGsとは?
SDGs(Sustainable Development Goals|持続可能な開発目標)とは2015年9月の国連サミットで採択された国際目標です。
誰一人取り残さない(leave no one behind)のスローガンのもとに、193か国の国連加盟国が2016年~2030年の15年間でSDGsの17の目標と169のターゲットの達成を目指しています。
SDGsのことについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
SDGsが必要とされる背景と歴史、SDGsの原則。そして、人(私たち一人ひとりの個人)と組織(企業や自治体)がSDGsを自分事として捉えるきっかけとなるような情報をお届けします。
SDGs2「飢餓をゼロに」とは?
飢餓とは何か、なぜ飢餓は起きるのか
飢餓とは、どのような状態を指すのか? 国連世界食糧計画(WFP)では以下のように飢餓の状態を定義しています。
“飢餓とは、身長に対して妥当とされる最低限の体重を維持し、軽度の活動を行うのに必要なエネルギー(カロリー数)を摂取できていない状態を指します”
現在、飢えに苦しむ人々は世界で8億1100万人に達している状況です。国連人口基金(UNFPA)が発表している「世界人口白書2021」によると、2021年の世界人口は78億7500万人。約10人に1人が飢えに苦しんでいることが分かります。
ところで、なぜ飢餓は起きるのでしょうか?
その最も大きな要因は戦争や紛争です。実に、世界で飢えに苦しむ人びとの6割は戦争や暴力にさらされた地域で暮らしていると言われます。命は助かっても、家や財産、仕事が奪われることによって飢餓に陥りやすくなります。
生活基盤を破壊するという面では地震・台風・洪水・干ばつなどの自然災害の被害も同様です。自然災害の規模や頻度は気候変動の影響で深刻化の一途にある点は看過できません(だからこそ、SDGsに取り組む必要性があります)。
また、食料の需給バランスの問題も無視できません。2010年と2050年を比較して、世界の食料需要量は1.7倍(58.17億トン)となると予測される一方で、年約13億トンが捨てられている現実があります(参考:世界の食料ロスと食料廃棄)。
さらに、新型コロナウイルス感染症による経済的な影響も無視できるものではありません。観光産業のように、産業によっては深刻な経済的損失を被る形となり、そこで働く人々が貧困・飢餓に陥るケースが増えています。
もちろん、絶対的貧困状態(生きていく上で必要最低限の生活水準に達しておらず、衣食住もままならない状態)にある人々にとって飢餓は常に付きまとう問題であることは言うまでもありません。
世界の栄養不足人口と蔓延率(PoU)の状況
国際連合食糧農業機関(FAO)によると、2021年に世界全体で7億200万人〜 8億2,800万人が飢餓に直面したと推計されています。残念ながら、SDGs2「飢餓をゼロに」のゴール達成からは遠ざかっている状況です。
“2021年には新型コロナウイルスによるパンデミックから世界が回復し食料安全保障が改善しはじめると期待されていたのに反し、各国間・国内の格差悪化を反映し、世界の飢餓はさらに上昇しました”
“予測では、2030年に6億7千万人が未だ飢餓に直面しているとされ、これは世界人口の8%、アジェンダ2030-持続可能な開発目標を開始した2015年と同じ水準です”
“2015年からほぼ一定水準であった栄養不足蔓延率(PoU)は、2019年から2020年の間に8.0%から9.3%に悪化、そして減速はしたものの、2021年に9.8%にまで悪化しました”
参考:食料安全保障と栄養の現状|国際連合食糧農業機関(FAO)駐日連絡事務所
さらに、今後はウクライナでの戦争が貿易経路・生産・価格面で世界の農産物市場に複数の影響を与え、近い将来、多くの国の食料安全保障と栄養摂取状況に影を落とす懸念があります。
食料不安の経験尺度(FIES)に基づく食料不安蔓延率の推移
食料不安の経験尺度(FIES)とは、飢餓の蔓延度とその複雑性を表す尺度です。
“FIESでは、所得や消費、栄養状態に基づいて飢餓を間接的に測定するのではなく、国別に約1,000世帯を対象に、食料不安に関する様々な経験について、8項目の質問を直接尋ねることで調査データを収集する。その回答を用いて、ある世帯が、中等度または重度の食料不安を経験する確率(SDG指標2.1.2)を推計する”
参考:SDG Atlas 2020|The World Bank
国際連合食糧農業機関(FAO)によって発行された『The State of Food Security and Nutrition in the World 2020: In brief』によると、重度の食料不安蔓延率(SDG 指標 2.1.2)は、2019年に世界全体で7億4,600万人と推計されていたものが、 『The State of Food Security and Nutrition in the World 2022: In brief』では9億2,370万人に増加しています。
日本における食料不安の経験尺度(FIES)に基づく食料不安蔓延率は世界的に見ると少ないものの、決して楽観視できるものではありません。
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
| 食料不安の経験尺度(FIES)に基づく、重度な食料不安の蔓延度(%) | 0.36493 | 0.3771 | 0.54644 | 0.70679 |
SDGs2「飢餓をゼロに」のターゲット
2.1|2030年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。
2.2 |5歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。
2.3|2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。
2.4|2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。
2.5|2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。
2.a|開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。
2.b|ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、全ての農産物輸出補助金及び同等の効果を持つ全ての輸出措置の同時撤廃などを通じて、世界の市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。
2.c|食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。
SDGs2「 飢餓をゼロに」の日本における達成状況
SDGsの達成・進捗状況を知る上では、Sustainable Development Report 2023 のデータが参考になります。
本レポートによると、SDGs2の日本における達成状況は「Significant challenges remain(重要な課題が残る)」、進捗状況は「stagnating(停滞している)」です。
<SDGs2の達成状況>
- Dashboards:Significant challenges remain
- Trends:stagnating
具体的に見ると、Sustainable Nitrogen Management Index(持続可能な窒素管理指数)の指標において「Major challenges remain(より重要な課題が残る)」とされています。環境への悪影響を抑える上で、適切な窒素管理が求められています(下記参照)。
“タンパク質などの生体分子に必要な窒素は,食料生産に欠かせない肥料要素であり,火薬や合成樹脂などの原料にもなる.大気の78%が窒素ガス(N2)であるとおり窒素そのものの賦存量は膨大である.しかし,どこにでもあるN2は,その安定さゆえに18世紀終盤まで人類による発見を逃れ続け,直接に利用できない物質であった.20世紀初期に確立したハーバー・ボッシュ法は,N2からアンモニア(NH3)を合成することを可能とした.このNH3をスタート物質として,人類は様々な反応性窒素(N2を除く窒素化合物の総称,Nr)を合成し,肥料や原料として使えるようになったのである.これは,世界人口と経済発展を支えてきた大きな恩恵である.しかし,人類の窒素利用には無駄が多く,環境への多量の Nr 排出を通じて地球温暖化,成層圏オゾン破壊,大気汚染,水質汚染,富栄養化,酸性化などの環境影響を引き起こしている.その被害コストは,1米ドル = 109円として世界全体で年間37~370 兆円とも推定されている(UNEP, 2019).人類の窒素利用は大きな便益と脅威を伴うトレードオフであり,窒素問題と称される.窒素問題の解決には,窒素の無駄を削減し,環境に排出される Nr を無害化し,余剰な需要を削減するといった窒素管理が求められる”
なお、その他の指標は全て「SDG achieved(SDGs達成)」の状態にあります。
SDGs2「 飢餓をゼロに」の企業の取り組み事例
むすびえ
むすびえは「こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくる」というビジョンの実現に向けた事業を展開しています。
“むすびえは、各地域のこども食堂ネットワーク(中間支援団体)がより活動しやすくなるための後押しを行い、こども食堂を応援してくれる企業・団体とこども食堂をつなぎ、こども食堂の意義や実態を伝え、理解を広げる調査・研究を行います。むすびえは、子どもたちと、こども食堂と、こども食堂を支援してくれる人たちの3者をつなぐ「むすびめ(場)」となりたいと思います”
参考:事業紹介|むすびえ
井関農機
「農家を過酷な労働から解放したい」という想いから始まった井関農機は、1926年(大正 15 年)設立の農業機械メーカーです。
世界のコメ生産量はアジアで全体の8割が生産されていますが、アジアの都市化に伴う農業の人手不足が課題となっています。井関グループでは日本で培った稲作技術を活かし、各地域に適した農業機械の提供を通して、アジア農業の機械化による生産性向上に貢献しています。
また、農地集積・規模拡大による生産性向上・農業従事者の減少・高齢化による人手不足などの課題を抱えている日本農業に対しても、ロボットトラクタなどのスマート農機やデータを活用したスマート農業の促進などで貢献しています。
キリン
キリンでは、レインフォレスト・アライアンス認証の取得支援をはじめ、スリランカの紅茶農園を長期的に支援し、認証茶葉の使用の拡大に貢献しています。
“キリングループでは生産地やそこで働く人とのより良いパートナーシップを築き、良質な原料茶葉を使用した「キリン 午後の紅茶」を提供し続けることができるように、「キリン スリランカフレンドシッププロジェクト」を実施しています。具体的には、「キリン 午後の紅茶」に使用している紅茶葉の産地であるスリランカの紅茶農園が、より持続可能な農園認証を取得するための支援と、農園の子供達が通う学校に図書を寄贈する2つの活動を行っています”
参考:スリランカにおける紅茶農園支援|原料生産地と事業展開地域におけるコミュニティの持続的な発展|キリンホールディングス
クボタ
クボタでは、食料の安定生産と農作業の効率化に向けて、生産から営農、販路拡大までを含めた、トータルソリューションで持続可能な農業の実現をめざしています。
“創業からクボタは徹底した現場主義で、各地の農家の事情に合わせた製品を開発・製造してきました。農業従事者が不足するアジアでは日本の稲作で培った製品と技術で生産性の向上に貢献。米需要が急激に伸びているアフリカでは現地の作業環境に合わせた農業機械の導入を段階的に推進しています。
また、農業でのデジタル技術活用が進むヨーロッパやアメリカでは現地の技術にマッチした農業機械を開発するなど、国や地域ごとに異なるニーズを汲み取り、世界中の現場を支え続けてきました。また、近年では農作物の高品質化や農業従事者の負担軽減など新しい農業の在り方を提案する営農面の施策や、販路拡大のサポートなどに注力。農業を生産だけでなく、その前後の工程とともにトータルに捉え、持続可能な農業を実現するソリューションの提供をめざしています”
ライスエクスチェンジ(Rice Exchange)×富士通
米取引のために作られた世界初のデジタル・プラットフォーム「ライスエクスチェンジ(Rice Exchange)」を開発したライスエクスチェンジ(Rice Exchange)社。同社はハイパーレッジャーファブリックを基盤とした拡張性の高いパーミッション型プライベート分散型台帳技術(DLT)ソリューションを構築するパートナーに富士通を選定しました。
“米は世界の多くの地域で主食となっており、何十億人もの人々が日々のカロリーの大部分を米から摂取しています。また、何百万人もの小規模農家がこの作物に依存して生計を立てています。米は古くから栽培されてきた作物です。ブロックチェーンを通じて、世界の米市場は一変する可能性があるでしょうか?Rice Exchangeはその可能性を信じています。彼らが開発したRicexマーケットプレイスは、富士通のブロックチェーンおよび分散型台帳技術(DLT)プラットフォーム上に構築されており、世界の米取引をより迅速に、より安全に、そしてより透明性のあるものにすることを目指しています”
参考:45兆円の米の取引市場の変革を目指して|Fujitsu Japan
本件にご興味のある方は農林水産省の公開する資料をご覧ください(グローバルな米取引のデジタルプラットフォームを構築することで、貿易コストの20%削減・取引時間の90%短縮、取引価格の適性化を実現しており、これは食糧問題の解決観点において価値ある成果と言えます)。
味の素
味の素は、2012年より、ベトナムの行政機関とともに日本の学校給食システムを応用した「学校給食プロジェクト」を開始。2023年3月時点で、学校給食プロジェクトの活動は62の自治体、4,262の小学校に広がっています。
“まずは、メニューブックや食育教材などの提供、そして給食運営と衛生管理を総合的に向上させるため、モデルキッチンを1校に設置。ここでベトナム味の素社が提案するメニューの給食をつくり、子どもたちに提供しました。この取り組みをベトナム全土の教育関係者に視察していただくことでモデルキッチンの採用校を少しずつ増やしていこうとしたのです。
また、栄養バランスがとれた献立を作成できるソフトウェアを開発、Webサイト上で公開しました。これは、食材を入力すると献立が表示され、摂取できる栄養素の量を算出するものです。これを使えば、調理スタッフが栄養に関する知識がなくとも、栄養バランスのよい食事を子どもたちに提供することができます。その後、教育訓練省や保健省等の中央政府の協力を得て、2017年度末までに2,910校に導入され、2018年5月には第2号のモデルキッチンを設置しました”
参考:学校給食プロジェクト(ベトナム)|Along with society|ESG・サステナビリティ|味の素グループ
また、同社ではベトナムにおいて子どもたちの栄養不足と肥満の問題が同時に起きている原因の一つに、栄養に対する正しい知識や経験が十分でないことを挙げ、正しい栄養情報を伝達できる人材の養成・活用を目的にベトナム国立栄養研究所(NIN)と味の素社で「ベトナム栄養関連制度創設プロジェクト(Vietnam Nutrition-system Establishment Project)」を2011年に創設。
2012年に教育訓練省が4年制の栄養学課程設置を承認し、翌年にはハノイ医科大学に栄養コースが開講。2017年には同国初の「栄養士」が43名誕生しました。
ケロッグ
ケロッグは、社会貢献プログラム「Better Days」を会社のESG戦略の柱に位置付け、世界中の人々が持続可能で公平に食糧へアクセスできる未来の実現に取り組んでいます。その結果として、2030年までに世界30億人の人々にとってよりよい日々(Better Days)の実現を目指しています。
“ケロッグの創業者W.Kケロッグは、強い社会奉仕の精神を持っており、現在のESG、SDGsの先駆けのような存在でした。W.Kケロッグは、1906年にケロッグ社を立ち上げて以来、事業の成長を目指す傍ら、1930年に、恵まれない子供たちをサポートするためのケロッグ財団を立ち上げるなど、生涯を通じてさまざまな慈善活動に尽力しました。このような創業者W.Kケロッグの遺志を受け継ぐ形で、現在我々ケロッグ社員が世界各国で取り組んでいる社会貢献プログラムがBetter Daysです”
参考:Better Daysについて| Kellogg’s Japan
また、近年課題となっている子どもたちの朝食欠食や孤食、栄養などの課題解決を目指し、ケロッグと認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえとの協働で「ケロッグ 毎日朝ごはんプロジェクト」を2022年6月29日に立ち上げました。
参考情報
本稿ではSDGs2「飢餓をゼロに」についての事例をお届けしてまいりました。もっと多くの事例を知りたい方、SDGs17の目標単位で様々な事例を知りたい方は下記の記事をご覧いただければと思います。
SDGs2「 飢餓をゼロに」について私たちにできること
募金・寄付をする
飢餓の問題は貧困問題と密接に関わっているため、募金や寄付を通じた支援によってSDGs2の目標達成に貢献することができます。
- WFP国連世界食糧計画(国連WFP)
国連WFPは女性と子どもの栄養強化、小規模農家の生産性向上と損失削減、国やコミュニティによる気候に関する災害への備えと対応支援、学校給食支援による人的資本の強化に取り組んでいます。
- ユニセフ(国連児童基金)
ユニセフは世界中の子どもたちの命と健康を守るために活動する国連機関です。保健、栄養、水と衛生、教育、暴力や搾取からの保護、HIV/エイズ、緊急支援、アドボカシーなどの分野で支援活動をおこなっています。
- TABLE FOR TWO International
TFTでは、東アフリカに位置するウガンダ、ルワンダ、タンザニア、ケニア、マラウイと 東南アジアのフィリピンの6か国で、学校給食プログラムと菜園・農業生産性向上プログラムの支援を行っています。
パートナーシップの輪を広げる
SDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」の観点で自分が起点・ハブとなり、自身が所属する会社や団体・地域コミュニティとパートナーシップ(協力関係)を築き、SDGsの取り組みを進める。
これも私たちにできることの一つです。
例えば、私たちプロジェクトデザインでは「SDGsについての理解・実践」を支援するツールとして様々なSDGsゲームをご提供しています。これらのゲームを活用することであなたの所属先やコミュニティでSDGsの取り組みを進めやすくなります。
・参考:SDGsゲーム
SDGsクイズ:「飢餓をゼロに」編
【問1】 撲滅するのは何?
“2030年までに、●●を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする”
これはSDGs2のターゲット2.1の内容です。この「●●を撲滅」に当てはまる内容として正しいものは次の選択肢のどれでしょうか?
<選択肢>
- 貧困を撲滅
- 飢餓を撲滅
- 飢饉を撲滅
- 災害を撲滅
正解は「飢餓を撲滅」です。
飢饉という言葉と間違える方もいらっしゃると思いますが、飢饉は「何らかの要因により人々が飢え苦しむこと」を指します。具体的には「特定地域における死亡率を急激に上げる極端な食料不足の事態」を指し、日本においては「江戸四大飢饉」が知られています。
【問2】 飢えに苦しむ人々の人数は?
“2022年現在、飢えに苦しむ人々は世界で●億●●●●万人に達している状況です”
この文中にある「●億●●●●万人」に当てはまる内容としてて正しいものは次の選択肢のどれでしょうか?
<選択肢>
- 7億1100万人
- 7億5500万人
- 8億1100万人
- 8億5500万人
正解は「8億1100万人」です。
【問3】WFPとは?
国連WFPの「WFP」の正式名称として正しいものは次の選択肢のどれでしょうか?
<選択肢>
- World Financial Programme
- World Fund Programme
- World Food Programme
- World Food Plan
正解は「World Food Programme」です。日本語だと「世界食糧計画」を意味します。
この記事の著者について
執筆者プロフィール
池田 信人
自動車メーカーの社内SE、人材紹介会社の法人営業、新卒採用支援会社の事業企画・メディア運営(マーケティング)を経て、2019年に独立。人と組織のマッチングの可能性を追求する、就活・転職メディア「ニャンキャリア」を運営。プロジェクトデザインではマーケティング部のマネージャーを務める。無類の猫好き。しかし猫アレルギー。
監修者プロフィール
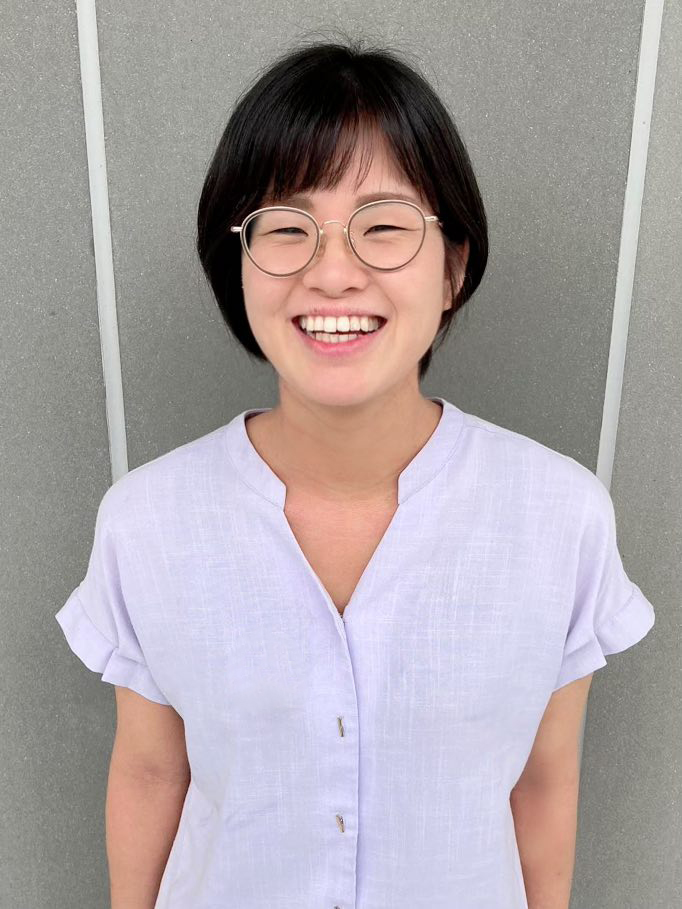
長瀬 めぐみ
岐阜県高山市出身、富山県滑川市在住。実家が100年以上続くお菓子屋を営んでおり、幼少期より観光や地域産業が身近な環境で育つ。高校時代、同級生が家業を知らない現実にショックを覚え、地域創生に関心を持ち始める。短大卒業後、すぐにUターン。まちづくりのNPOで子どもの教育支援や大学のない中山間地域へ若者を誘致するインターンシップ、農業支援などの取り組みで4年間で延べ600人以上の学生と関わる。様々な活動の中で、地域が元気になるためには、地元の若者が育つ仕組みと地域の大人が楽しんで地域に参画する土壌づくりの必要性を感じ、公立高校で学校と地域をつなぐコーディネーターなども務めた。体験から気づき、意識・行動変革をもたらすゲームコンテンツに魅力を感じ、全国に広めたい!とプロジェクトデザインに参画。地元飛騨が大好き。
Contact Us
お見積り依頼の他、ちょっと知りたい・とりあえず聞いてみたいことへの相談にも対応させていただいております。是非、お気軽にお問い合わせください。
<相談内容の例>
- 数あるSDGsゲームの中から自社に合うゲームを知りたい
- SDGsゲーム研修の具体的なプログラム内容を相談したい
- オリジナルのSDGsゲームの開発に興味があるので話を聞きたい