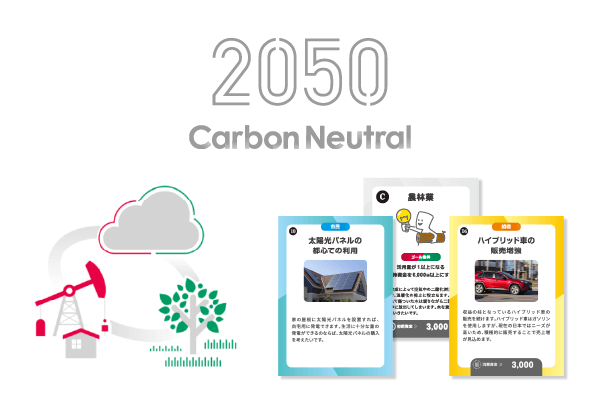ホーム > カードゲーム「2050カーボンニュートラル」 > カードゲーム「2050カーボンニュートラル」ブログ一覧 > 自分ごと化のきっかけに!業務で実践できる脱炭素アクションのご紹介

自分ごと化のきっかけに!業務で実践できる脱炭素アクションのご紹介
- 最終更新日:2026-01-07
企業において、脱炭素は団体戦と言われるように、2050年カーボンニュートラルという目標は経営層やサステナビリティ部門だけの課題ではありません。
自社のカーボンニュートラルを実現するためには Scope3 を含めた全ての事業活動における温室効果ガスの排出量をネットゼロまで削減する必要があることを鑑みると、企業の温室効果ガス排出量削減目標達成のためには従業員一人ひとりの意識と行動の変革が不可欠になります。[1]

Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)
Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)
もちろん、従業員が幅広く関与する Scope3 の活動(通勤や出張、備品の購入等)は、企業全体の温室効果ガス排出量の中では大きなボリュームを占めないこともあります。
しかしながら、削減量の多寡に関わらず、従業員全体が取り組むことができる脱炭素アクションには従業員一人ひとりの意識を確実に変えていく効果があります。そして、その先に脱炭素に向けて団体戦で戦っていくための土壌・空気感が形成されていきます。
そこで本稿では、従業員が業務で実践できる「脱炭素アクション」をご紹介するとともに、一人ひとりの行動の変革が、組織全体にとって何を意味するのかを推考していきたいと思います。
業務で実践できる!脱炭素アクション
IT機器利用とデータ通信における排出削減
業務のデジタル化を進めつつ、その業務のデジタル化を脱炭素の観点から見直すことで、CO2の排出量を削減可能です。
- デジタル署名・クラウド共有を徹底する
契約書や稟議書は可能な限り電子化し、クラウド上で共有・承認を完結させます。これにより、紙の使用量だけでなく書類を運ぶ移動時間と電力も削減できます。 - PC設定の見直しと徹底
画面の輝度を下げ(例えば、輝度を100%から70%に下げるだけで約20%の節電効果があると言われます)、15分以上離席する場合はスリープモードを利用します。 - 「データ整理」を習慣化する
不要なメールやクラウドストレージのファイルを定期的に削除します。データセンターのサーバーも電力を消費してデータを保持しているため、デジタル断捨離は立派な脱炭素アクションです。
ICTを活用した移動・出張に伴う排出の削減
ICT(情報通信技術)を活用したテレワークやリモートワークの導入は、最も大きなCO2削減効果が期待できる脱炭素アクションです。
- 通勤に伴う排出の削減
自家用車通勤者の減少により、ガソリンなどの燃料消費に伴うCO2排出量が直接的に削減されます。また、バス・鉄道などの公共交通機関の利用が減ることも、交通全体のエネルギー消費効率の改善に寄与します。 - 出張・移動の削減
Web会議システムや電子契約の導入により、国内外の出張や業務関連の移動(飛行機や車等)が減少し、移動に伴うCO2排出を削減できます。やむを得ず出張や外回りをする際は、可能な限り公共交通機関を利用し、長距離移動は新幹線や電気自動車(EV)などの排出量の少ない手段を優先的に選択します。 - オフィス電力の削減(副次効果)
出社率が下がることで、オフィス全体の照明、空調、データセンター等の電力使用量を抑えることができます。また、テレワークの定着に伴い、オフィスを縮小・最適化(オフィス面積の削減)する事例も見られ、これにより恒常的なエネルギー消費を削減できます。
例えば、日本政策金融公庫による脱炭素の取り組みに関する調査[3]では、コロナ禍以降の変化もあり、「人の移動の抑制」に取り組む企業は回答企業全体の44%に上っています。もちろん業種・業態により差異があり、情報通信業(64.7%)や卸売業(54.7%)などが高い割合を示す一方で、運輸業(26.0%)や飲食店・宿泊業(28.0%)のように実施の難易度が高い業態もあります。
働き方改革とオフィス使用エネルギーの抑制
働き方改革を脱炭素の観点からも再評価することもできます。残業時間の削減や定時退社の徹底など、労働時間短縮はオフィスでのエネルギー消費を直接的に抑制します。
- ノー残業デーの設定や定時退社の徹底
従業員がオフィスに滞在する時間が減り、夜間の照明、空調、PCなどの機器の稼働時間が減り、電力消費とそれに伴うCO2排出量が削減されます。また、終業時刻に合わせた空調の停止や一斉消灯なども徹底しやすくなります。
従業員の自宅における排出削減への取り組み
リモートワークが普及する中で、従業員の自宅における電力消費も、企業の Scope3 排出量(従業員の通勤・移動以外)の一部として、間接的にカウントされる場合があります[4]。
- 電力プランの見直し
従業員の自宅の契約電力を再生可能エネルギーを供給する電力会社に切り替えることを検討します。これは、家庭からの排出を減らす最も効果の高い脱炭素アクションの一つです。そのひとつの事例として、みんな電力が提供する「自社社員の再エネ切り替えサポート」があります。みんな電力では、法人向けと個人向けの双方で再生可能エネルギーの電力プランを提供していますが、「社員の再エネ切り替えを通じて脱炭素社会の実現を加速する」という趣旨に賛同したみんな電力の顧客企業の一部(アシックスやZozo等、2022年のリリース時点で24社)では、自社従業員に向けて自宅の電力の切り替えを呼びかけています。
脱炭素アクションの推進と同時に必要なこと
従業員による脱炭素の行動が習慣化して成果をあげるためには、脱炭素アクションの推進と同時に、その取り組みによる成果を目に見える形にすることも必要です。
従業員の脱炭素アクションを見える化(定量化)することのメリットは、以下の点にあります。
- モチベーション向上
CO2削減という抽象的な目標に自信の行動がどのように貢献しているのか?(CO2削減、コスト削減など)が明確になるため、自分事としての意識が高まり、継続的な行動の動機付けとなります。 - 行動の具体化
削減量が可視化されることで、「どの行動」が最も効果的かが分かり、より効率的でインパクトの大きな脱炭素アクションを選択できるようになります。 - 企業文化への定着
貢献度がランキングや表彰を通じて社内で共有されることで、脱炭素への取り組みが単なる義務ではなく、前向きな企業文化として定着していきます。
行動の「見える化」の鍵になるのはデジタル技術です。そこで、デジタル技術を活用して従業員一人ひとりの脱炭素行動を「見える化」し、行動変容を促している事例を紹介します。
クレディセゾンの事例
クレディセゾンの「セゾンエコチャレンジ」は、社員の環境意識向上と行動定着を目的とした、約4,000名の全社員参加型のCO2削減プロジェクトです[5]。
参加者はWebアプリケーション「becoz challenge」を活用してマイバッグ・マイボトルの使用、フードロス対策(値引き商品の購入)、ペーパーレス会議といった日常のエコアクションを写真で投稿します。
このアプリの最大の特長は「見える化」です。投稿されたアクション数に応じ、事前にシミュレーションされたCO2削減量がリアルタイムで可視化されます。全期間で40tのCO2削減という具体的な目標を掲げ、従業員一人ひとりの小さな行動の変化が、企業のサステナビリティ目標達成に繋がることを実感させる仕組みです。
NTTドコモビジネス(旧社名:NTTコミュニケーションズ)の事例
NTTドコモビジネスの「Green Program for Employee」は、企業のカーボンニュートラル達成に向け、従業員一人ひとりの環境意識向上と行動変容を促すデジタルプログラムです[6]。
このプログラムにおいて、従業員はリモートワークの実施・公共交通機関の利用、・省エネ行動などの日々のエコアクションをデータとしてアプリに記録・計測します。これにより、個人の行動が具体的にどれだけのCO2削減に貢献したか(CO2換算など)が可視化されます。
さらに、収集したデータをもとに企業全体の目標達成度に対する個人の貢献度を明確にし、ランキング形式やゲーミフィケーション要素を取り入れることで取り組みのモチベーションと継続性を高めることで、企業の環境目標達成を従業員自らの主体的な活動として加速させています。
また、同社では従業員一人ひとりのエコアクションから脱炭素活動を加速させる「従業員参加型エコアクションチャレンジ(ONE TEAM CHALLENGE)」を開催。幅広い業界の13社の従業員1,348名による約3万回のエコアクションの実践され、約15トンのCO2削減を達成しています[7]。
従業員の脱炭素アクションの実践におけるポイント
従業員(広義には各部門)の脱炭素アクションの取り組みを進めていく上では、自社の脱炭素の取り組みの全体感と従業員一人ひとりの貢献がどのように全体の目標に繋がっているのかを理解できる形で、当事者たる従業員に伝わっていることが重要です。
また、インパクトの大きい分野(Scope1、Scope2の自社の排出、Scope3の製品の使用に伴う排出の抜本的な削減等)に取り組まないまま従業員だけに努力を促すことは、グリーンウォッシュのように映ることもあるかもしれません。
そうならないためにも以下のような取り組みや仕組みが重要になります。
- 排出量データの可視化
排出量算定サービスを活用して、全社排出量の内訳(Scope1, 2, 3)や部門別の削減進捗を社員がいつでもアクセスできるダッシュボードで公開します。 - 長期的計画の周知徹底
カーボンニュートラル目標に向けた長期的計画の周知[8]を行います。自社の温室効果ガスの排出量の大部分を占める対象について、現時点では技術的な理由もしくは経済的な理由で対策の導入が困難な場合、技術開発のロードマップや将来的な導入計画などを明らかにすることも重要です。 - 「脱炭素に関わる予算」の部門配分
環境対策に関する予算を設け、その一部を特定の排出削減テーマ(例:オフィスのエネルギー使用の削減)として各部門に配分します。予算の「オーナーシップ」を与えることで、部門の当事者意識を高めて高い実践率が期待できます。私たちプロジェクトデザインが企業のサステナビリティ研修やワークショップを実施する中でも、参加者から「変化の起点」として提案されることの多いアイデアでもあります。 - 定期的なフィードバック
各部門の脱炭素の貢献度についてサステナビリティ部門や担当者が「ありがとう」の言葉と共に具体的なデータを用いてフィードバックする「貢献レポート」の発行を行うこともひとつの手法です。非財務的な報酬(承認欲求)を満たし、継続的な行動を促します。
プロジェクトデザインが2024年12月に実施した1,032名の会社員を対象とした「企業のサステナビリティに関するアンケート」調査では、自身の所属する会社でサステナビリティ領域に関する何らかの取り組みを行っているかどうかわからない(認知していない)人が34.4%[9]の割合となりました。
また、同アンケートにて「所属する会社のサステナビリティ領域に関する取り組みが効果を発揮しているか」を伺ったところ、サステナビリティ関連部署の人の72.7%が効果を発揮していると答えたのに対して、サステナビリティ関連部署外の人で効果を発揮していると答えた人は22.2%に留まります[10]。
こういった回答の背景には、会社のサステナビリティ領域に関する情報が、社内に上手く共有されていない状況があることが考えられます。より詳しいアンケート結果がお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
・【調査報告】1,032人へのアンケートで分かった!企業のサステナビリティ推進における「環境価値・社会価値」と「経済価値」の両立を阻むハードル
脱炭素アクションの習慣化が、カーボンニュートラルの「自分ごと化」のきっかけに
本稿では、従業員一人ひとりが業務で実践できる脱炭素アクションをご紹介してきました。
従業員による小さな脱炭素アクションの積み重ねは、最終的には Scope3 を含む企業全体の排出量削減という成果につながります。また、排出量削減と同時に重要なのは、アクションを重ねる過程で個々人の意識が変化していき、周囲へ伝播し習慣化され、企業の組織分化へも好影響が及ぼされることです。
私が企業のカーボンニュートラル担当者やサステナビリティ部門の方からお伺いするのは、組織全体としてカーボンニュートラルの取り組みを進めていく上で、心理的な壁(他人事の壁や無関心の壁、保留の壁等)を乗り越えて、一人ひとりが問題を「自分ごと」として捉え、協力していける関係をつくることが非常に重要だということです。(詳細は別ページ:組織でカーボンニュートラルが進まない2つの問題と4つの壁、カードゲーム「2050カーボンニュートラル」の活用提案にありますので宜しければご覧ください)。
自社の温室効果ガス排出量を2050年に向けて実質ゼロにする「カーボンニュートラル目標の達成」において、本稿でご紹介したような脱炭素アクションの取り組みは、削減量の多寡によらず目標達成に向けて必要不可欠なものになります。
それと同時に、一人ひとりの脱炭素アクションから組織全体で意識と行動が変わり、「壁」を乗り越えて互いに連携していくことで、カーボンニュートラルに資する設備投資やサービスの導入、設計変更や低炭素な調達、脱炭素領域での新規ビジネスの考案など、より排出削減量が大きく、また企業の事業リスク低下や収益向上につながる取り組みが会社全体で促進されていきます。
[1] [2] 参照)政府のグリーン・バリューチェーン・プラットフォーム
[3] 参照)日本政策金融公庫「中小企業の脱炭素への取り組みに関する調査」(中小企業の脱炭素への取り組みに関する調査
[4] テレワークに伴う排出については、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算 定に関する基本ガイドライン (ver.2.5)『2.7【カテゴリ7】雇用者の通勤』」の算定対象範囲 において、「本カテゴリにテレワークによる排出を含むこともできます」との記載があり、 カテゴリ7(雇用者の通勤)に任意で含めるという整理となっています。参照)環境省「サプライチェーン排出量算定におけるよくある質問と回答集」
[5] 参照)株式会社クレディセゾン「全社員参加型のCO2削減プロジェクト「セゾンエコチャレンジ」開始~専用アプリでCO2排出量を可視化~」
[6] 参照)NTTドコモビジネス「GXソリューション」
[7] 参照)NTTドコモビジネス「「Green Program for Employee™」-CO₂排出量の可視化から始まる従業員の意識向上」
[8] 事業報告書や会社案内、自社ウェブサイト等(上場企業であれば、統合報告書やサステナビリティ・レポート、IR説明会など)を通じて公表するとともに、社内に対しても社内報やイントラ、従業員説明会などの方法を組み合わせることでコミットメントを複合的に周知する
[9] 調査結果②会社の「サステナビリティ領域に関する取り組み状況」参照)【調査報告】1,032人へのアンケートで分かった!企業のサステナビリティ推進における「環境価値・社会価値」と「経済価値」の両立を阻むハードル
[10] 調査結果④ 立場の違いで見る「会社のサステナビリティ領域の取り組みに思うこと」参照。1つ目の質問項目(所属する会社のサステナビリティ領域に関する取り組みは効果を発揮していますか?)に「当てはまる」「やや当てはまる」と回答をされた人の割合は、サステナビリティ関連部署の人の72.7%に対して、サステナビリティ関連部署外の人は 22.2%に留まります。参照)【調査報告】1,032人へのアンケートで分かった!企業のサステナビリティ推進における「環境価値・社会価値」と「経済価値」の両立を阻むハードル
ご案内
過去から現在にかけて私たちが行ってきた様々な活動が地球環境にどのような影響を与えているのかをマクロ的に俯瞰することによって、私たちの価値観や考え方に気づき、行動変容に働きかけるためのシミュレーションゲーム。
それが、カードゲーム「2050カーボンニュートラル」です。
ゲーム体験を通して「なぜカーボンニュートラルが叫ばれているのか?」、そして「そのために、わたしたちは何を考えどう行動するのか?」に関する学びや気づきを得ることができます。
組織内のサステナビリティ推進に向けた研修や、社内外とのステークホルダーとのサステナ推進の協働体制づくりにご活用いただけます。

ゲームの活用用途が決まっていない、ゲームに興味はあるが具体的な活用法がイメージしづらい方向けに、活用提案のコンテンツをご紹介します(カーボンニュートラル推進における問題の観点からカードゲーム「2050カーボンニュートラル」の活用方法をスライドを交えながら、分かりやすくご提案します)。
この記事の著者について
執筆者プロフィール

南原 順(なばら じゅん)
島根県浜田市生まれ。京都大学大学院地球環境学舎修了(修士・環境政策専攻)。2005年より南信州を中心に、市民が出資・参加する自然エネルギー事業の立ち上げ及び運営に携わる。その後、ドイツを拠点に欧州4カ国での太陽光発電プロジェクトの開発・運営を経験。帰国後は日本企業にて国内のメガソーラーの事業企画、開発を行う。2016年にコミュニティエナジー株式会社を設立し、島根県浜田市を拠点に地域主導の自然エネルギー導入の支援を行う。セミナー等での講演や企業・自治体向け職員研修・ワークショップの実績多数。
Contact Us
お気軽に、お問い合わせください